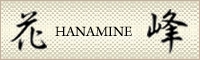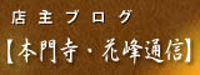インターネット墓
現代では「散骨」や「樹木葬」など、お墓の埋葬方法や葬儀の方法まで多様化が進んでおります。
昨今、これからのお墓の形として注目されているお墓に「インターネット墓」という形態も出現しはじめておりますので、今回はこちらをご紹介させていただきます。
そもそも、墓には「遺骨」を収容する役割と、遺族がお参りする役割との両方がありますが、散骨や樹木葬などで遺骨を収納する必要のないお墓が登場したことによって〝参る〟ためのお墓として用意され始めたものです。
元来、遺骨にこだわるのは儒教の影響で、「仏教」では遺骨には意味が無いとされています。
実際に仏教の発祥地でもあるインドでは遺骨は川へと流される散骨がメインです。
人がお墓を作る意味は供養であり、その人がこの世に存在したという記録である、という考えかたがありますが、もしそうだとしたならば、インターネット墓は、納骨を必要としない人にとって、充分にお墓としての役割を果たしてくれるのかもしれません。
通常のインターネット墓は、マウス操作によって画面上の墓石に「供物」を供えたり、「線香」をあげたり、水をかけたりしてネット上でお参りするものです。
お経を流すこともできます。
掲示板に記帳して、お墓参りの痕跡を残すこともできます。
また、「霊園」によっては、親族専用にホームページを開設するというサービスを提供してくれる所もあります。
そこには故人の経歴や写真が見れたり、故人の声が聞けたりします。
これは「お墓」を購入した人へのサービスですが、将来的には、このサービスのみが独立していく可能性も充分にあるように思えます。
この記事を読んだ方は以下の記事も読んでいます:
タグ
2012年4月4日 | コメント/トラックバック(0) |